人物 Archive
第十八回 「重源上人」・・(平成19年8月1日)
現在、僧侶といえば葬式に従事する者と思われがちです。というのも、私たちは通常、僧侶に出会う機会といえば、葬式や法事がほとんどで、僧侶は境内墓地や納骨堂のいわば管理者となってしまっていると言えるからです。
「葬式仏教」という言葉がありますが、仏教者のそうした揶揄が込められているのではないでしょうか。もっとはっきり言うと、葬式仏教は仏教の堕落した姿と考えられているのではないでしょうか。近年は、自然葬や散骨など、いわば「自然に還す」葬送が注目されていますが、こうした風潮も、葬式仏教への批判とも取れるのではないでしょうか。
ですが、考えてみると、僧侶がきちんと葬式を執り行ってくれるということは、一人の人間にとって、誕生と並ぶ死という人生の重大事を厳粛に通過したいという願いに応えていることも間違いないと思われます。葬式は死者の救済に関わる儀礼ですし、残された者にとっても儀礼的意味合いは濃いですが、死者に別れを告げる行為は、大変重要なことだと思います。
僧侶が葬送に従事するようになったのは、所謂「聖」に代表されるような、遁世僧の活躍があって以後のことです。奈良の南都六宗や比叡山などの所謂官僧は、葬送には関与しませんでした。東大寺や延暦寺などでは、現在、葬儀もおこなっておりますが、これは第二次大戦後のことで、それまでは身内の葬式でさえ遁世僧系の他宗派の僧侶に任せていたのです。
こうした、官僧と遁世僧の葬送に関する相違は一体なにに起因しているのか、と言いますと、官僧はいわば官僚的な存在で、鎮護国家などの国家行事に関わっていることがあります。葬儀は死穢です。古代中世にあっては、死穢を避けることは重大な関心事であり、特に官人・官僧にとっては非常に重要なことでした。
一方、遁世僧はこうした制約から自由な存在でした。というよりはむしろ積極的に関わりを持っています。これまでに述べてきた中で、幾度か聖について述べてきましたが、彼らの中には、奈良時代の行基集団の流れを汲んで、勧進をおこなう一方、民衆救済に尽力する者が多く存在しました。平安後期になると末法思想が流布し、相まって浄土信仰が広く世に浸透しましたが、そうした時代背景の中で、聖の民衆救済の活動と民衆の来世への願いが、「葬送」という儀式で結びつくことはとても自然なことだと思われます。
こうした遁世僧の葬送活動の理論的な背景を構築したのが、これまでに述べてきた良源・源信・覚鑁といった僧侶でした。
鎌倉時代、こうした遁世僧の最初の第一人者といえば、俊乗房重源です。重源の歴史的な最大の功績は、源平合戦の最中に消失した東大寺復興に尽力したことが挙げられます。重源は東大寺復興の勧進事業を通じて、世に「舎利信仰」「舎利塔信仰」を広めましたが、その中で五輪塔も全国に普及させました。
重源は、宋の浙江省にある阿育王寺で、舎利塔・仏舎利信仰を目の当たりにし、大いに触発を受けたようです。阿育王寺はインドのアショーカ王にちなんだ寺院です。アショーカ王は、仏教に帰依してより、様々な社会事業を興し、インド全土に八万四千の舎利仏塔を建てたとされる王です。まさに遁世僧の先駆的な存在と言えますね。
帰国後の重源は、法然の門下に入り、後に高野山に移りますが、こうした中で遁世僧として勧進僧としての活動を開始します。彼の伝記と、勧進僧としての活動については『南無阿弥陀仏作善集』という史料に見ることができます。重源は勧進によって東大寺他多くの寺院の建立・修復に尽力していますが、これに平行して各地に浄土堂や入浴施設を建て、民衆救済に尽力しています。また迎え講を盛んにおこない多くの人の阿弥陀仏の救済の喜びを伝えました。
そして重源でもっとも注目されるのが、先に述べた「舎利信仰」「塔信仰」です。重源は各地より多くの仏舎利を集め、これを独自の舎利容器に入れ、各地の寺院に納めました。特に水晶製の五輪塔に納めた仏舎利は貴重な文化財として保護されています。こうした熱心な舎利塔信仰は、やがてお墓や供養塔として各地の石塔建立の火付け役になったことはいうまでもありません。
こうした流れに期を一にして、中国より優れた石材技術が日本に伝えられます。その代表的存在が、伊行末です。彼は東大寺再建に、重源と共に尽力し、その際に彫刻された東大寺法華堂前の石灯籠は、国の重要文化財に指定されています。
彼らの伝えた技術の中で特に注目されるのは、硬石の花崗岩を加工する技術です。それまでの日本の技術では、凝灰岩などの軟石を加工できるにとどまっていたのですが、硬石の加工技術の伝来によって石材工芸の幅が飛躍的に広がりました。そして、現代のお墓は、そのほとんどが御影石などに代表される、硬石です。
重源と伊行末の時代に、現代墓地の様式の原型ができあがりつつことが見てとれるのではないでしょうか。
第十七回 「覚鑁その三」・・(平成19年7月1日)
さて、『五輪九字明秘密釈』の内容は、非常に難解とされ、中国の陰陽五行説・道教の身体観や俗信が入り交じっていて、その解明だけでも大変苦労する書物です。加えて、本文のほとんどが五輪の真言=マンダラと、阿弥陀小呪の真言=マンダラの梵字に関した微細な説明の連続のために、非常に複雑な内容となっています。
なので、その詳細な内容については、ここでは触れません。「大日=阿弥陀」「即身成仏=往生」は真言密教の教理の中では矛盾しないことである、という点が本書の主題であることは、すでに先月お話ししたように、序文で確認できますので、「五輪塔」がいかにそのことを表現しているのか、を解説していくことにします。 まず密教の最終目的が「即身成仏」であることは明確です。「即身成仏」とは「私たちがいま生きている、この身このまま(即身)」で、誰でも「成仏」できる、あるいはその可能性を持っている、ということです。では、密教ではどのようにして「即身成仏」するのでしょうか?
真言宗開祖・空海には『即身成仏義』という著作があります。この中で空海は、本来、我々すべてに、宇宙=大日如来と同じ「六大」(「体大」大日の本質)・「三密」(「用大」大日のはたらき)・「四曼」(「相大」大日の姿)が備わっているので、必ず「即身成仏」できると述べています。しかし煩悩のためにそれらを正しくとらえることができません。そこで修行して本来の姿を取り戻す必要があります。この修行を「三密」と言います。そして「三密」を正しく実践するための宇宙観が「六大」「四曼」です。
「六大」とは空海独自の教義で「五大」(地大・水大・火大・風大・空大)=「五輪」に「識大」を加えたものです。宇宙そのものの真理である大日如来と修行者は、本質的に同じであり、一体となることができる。その根拠が「六大」であるとされます。本質的に同じであるが故に、修行者は現世に於いて成仏、つまり「即身成仏」できるということになります。
その六大とは、それぞれに次のようなことを指します。
「地大」大地が一切のものを載せ、ものの拠り所となる堅固さ、安定感に満ちた性質を現す。坐禅修行者の足に当たる。ア・四角・黄色に象徴される。
「水大」一切のものを清め、爽快感を与え、ものを育成させる柔軟性があり、復元力に優れた性質を現す。坐禅者のへそに当たる。ヴァ・円・白に象徴される。
「火大」一切のものを焼き尽くす烈しさとともに、温かさを現す。坐禅者の心臓に当たる。ラ・三角・赤に象徴される。
「風大」一切のものを吹き飛ばす活動性、ダイナミックな性質を現す。坐禅者の首に当たる。カ・半月・黒に象徴される。
「空大」虚空が無限できわまりないように、底知れない包容力を現す。坐禅者の頭に当たる。キャ・宝珠・青に象徴される。
そして「識大」は、これら「五大」の性質を見る主体(つまり自分)のことを言います。
空海はこれを総合して「六大は無碍にして常に瑜伽なり」つまり「見られる五大も、見る主体の識大も区別されることなくひとつに統一されている」と言ってます。「六大」は大日如来の身体=宇宙全体であると同時に、修行者のからだでもある故に、「大日如来と修行者は本質的に同じ」であり、これこそが「即身成仏」できる根拠となります。
次に「四曼」(相大=大日の姿)とは、「大曼陀羅(諸仏・諸菩薩など諸尊の形像で現す)」「三昧耶曼陀羅(諸尊の持ち物で現す)」「法曼陀羅(諸尊の種子で現す)」「羯磨曼陀羅(諸仏菩薩の手足の動作で現す)」四種類の曼陀羅です。密教に於ける曼陀羅は、『大日経』を根拠として「五大」の世界を表現した「胎蔵界曼陀羅」と、『金剛頂経』を根拠に「識大」の世界を表現した「金剛界曼陀羅」があり、このふたつの曼陀羅を「両界曼陀羅」もしくは「両部曼陀羅」と言い、このふたつの曼陀羅一対で大日如来の世界を表現しています。
そして「三密」(用大=大日の働き)とは、「即身成仏」するための三つの修行のことです。それぞれ「身密」(「印契」手に印を結ぶ)、「口密」(口で「真言」「陀羅尼」を唱える)、「意密」(集中して「三摩地」の境地に入らせる)と呼ばれます。修行者は、本尊の前で坐禅を組み、手で印契を結び、口に真言を唱え、心を集中させて、三密をおこない、大日如来と一体にならんとします。これが「即身成仏」のための修行です。
やや長くなりましたが、これが「五輪塔」を理解するための最低限の知識です。そして、これに基づいて覚鑁は図のような「五輪塔図」を描きました。
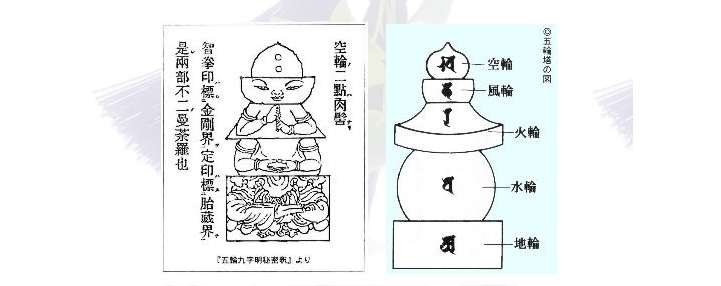
横に五輪塔の略図を並べてみましたが、並べ較べてみてわかるように、覚鑁は五輪塔に「三密加持行」をすべて実践している修行僧の姿をなぞらえていることがはっきりと見ることができます。つまり「五輪塔とは密教の即身成仏を完成した姿」であると言えます。
具体的には、①「五輪塔」は胎蔵界・金剛界の大日如来が坐禅(三摩地)をしている姿で「意密」を示しており、それは②「水輪」の印契(「定印」)が「胎蔵界の大日」を現し、「火輪」の印契(「智拳印」)を現して、「両界不二」を示し、③同時にそれは印契によって「身密」を現し④五大の梵字(ア・ヴァ・ラ・カ・キャ)があることで「口密」を示すのです。
この「五輪塔」が石塔としてお墓に用いられ、後に「納骨器」としても使われたということは、「五輪石塔は死者の成仏」を意味していることになります。そして逆に「五輪塔に埋葬すると、あるいはお墓に建てると、死者は皆成仏できる」という展開も見えてきます。
覚鑁は、こうした理論づけをおこなっただけではなく、配下の高野聖を用いて全国に普及させました。それだけではなく、先に述べたように『五輪九字明秘密釈』にて、当時世を席巻していた浄土教の教えを密教に取り込むことでより民衆に深く浸透させることを可能にしたのです。
こうして五輪塔は、平安末期から約800年間にわたってお墓の中心的存在として建立され続けることになるのです。
第十六回 「覚鑁その二」・・(平成19年6月1日)
覚鑁の代表的な著作に『一期大要秘密集』『五輪九字明秘密釈』があります。このふたつの著作を見ながら、覚鑁が、日本の葬墓に与えた影響を見ていくことにしましょう。
「一期大要」とは「人の一生で一番大切なこと」という意味です。本著の冒頭で覚鑁は「人生で一番大切なことは最後の心の持ちようにある」と述べています。『一期大要秘密集』の原文は漢文ですが、その冒頭部分の現代語訳を以下に掲載します。
************************************************************
よく考えると人の一生で一番大切なことは、最後の心の持ち方にある。九種類の人間の往生は、臨終の正しい念仏にかかっている。成仏を求める者は、当にこのことを習得するべきである。出家した者の生死はこの瞬間で決まる。そこで今、密教の教えからそのエッセンスを集めた。九種類の心の用い方として、極悪の罪業を払い、極楽往生の九種類の蓮華台に乗ることを願う。もし最後の臨終の手順が正しいものなら、破戒の僧尼も必ず往生できる。悪いことをした男女も必ず極楽に生まれる。まして智恵があり戒めを守った者なら言うに及ばない。善男善女ならなおさらだ。これがすなわち真言の秘密の観法の効力である。深く信じてつまらぬ疑いを持つことがないように。
*************************************************************
そして最終章「九、没後追修の用心門」では、「地獄に堕ちる人は十五種の状態になる。餓鬼道に堕ちる人は八種の状態になり、畜生道に堕ちる人は五種の状態になる。」と経文を引用しつつ詳細に説明し、具体的な方法や真言による供養法について記し、急いで死者を苦しみから救え、と説いています。
ここに、鎌倉時代以降盛んになる「追善供養」(四十九日や年回忌などの法要)の原型を見ることができます。
次に『五輪九字明秘密釈』について見ていくことにしましょう。
タイトルの「五輪」とは「地水火風空」の「五大」で「ア・ヴァ・ラ・カ・キャ」の大日如来の真言のことです。そして「九字」は阿弥陀仏の「小呪」といって「オン・ア・ミリ・タ・テイ・セイ・カ・ラ・ウーン」の九文字の真言を指します。
「明」とは「真言」「呪」「陀羅尼」の意味、「秘密」は「密教」、「釈」は言うまでもなく「解釈」なので、「大日と阿弥陀の真言の密教的解釈」という意味になります。そして大日如来は真言宗の、阿弥陀仏は浄土宗の、それぞれの御本尊ですから、おのずと本書の意図が明確になりますね。
真言宗とは「即身成仏」の言葉に代表されるように、今生きている現世に主眼を置いた宗派です。恐らくは空海自身が非常に現実主義的な考えの持ち主だったせいもあるのでしょう、真言宗ではあまり未来のことが語られておりませんでした。
ですが、真言宗も仏教の一宗派であり、仏教は来世以降(未来)における成仏を求める宗教である以上は、浄土思想と全く無縁ではあり得ません。覚鑁より先の「高野聖」達の間では、すでに「真言念仏」はおこなわれていました。これを、覚鑁が一連の著述にまとめ、理論的にまとめ上げたことで、真言宗の表舞台に現れ、真言宗の教義に新たな展開が開けたと言えるのです。
では、そのことの歴史的意義とはなにか?といえば、後の日本のお墓の意味・考え方・建墓や供養の方法といった日本の葬墓に関わる文化が五輪塔を通じて全国に広まっていくことになるのですが、覚鑁の『五輪九字明秘密釈』は、その基本概念となっていることにあります。
結論から言えば、五輪塔のお墓には「死後は成仏し往生できる」という意味が込められています。これは、真言宗の「即身成仏」の思想と、浄土教の「極楽往生」の思想が融合することで、はじめて明確に理論づけが可能になったのです。
五輪塔は「成仏と往生」というコンセプトを明確に打ち出したお墓ということができます。そしてこのことがその後の日本人のお墓の標準的な意味となったのです。
次回は、『五輪九字明秘密釈』を読み解きながら、五輪塔についてもう少し詳しく述べてみたいと思います。
第十五回 「覚鑁その一」・・(平成19年5月1日)
興教大師覚鑁(1095~1144)は「真言宗中興の祖」と称される平安後期の僧侶です。
真言宗は、空海以後、教学的にはあまり発展しなかったのですが、覚鑁は「伝法会」を復興し、当時流行の浄土教を真言教学に於いていかに捉えるかを理論化しました。また、覚鑁が晩年過ごした根来寺を本山とする「新義真言宗」や新義真言宗から分派した「豊山派」「智山派」の開祖としても知られるように、真言宗の教義に新たな展開を開きました。
13歳で得度出家した覚鑁は、35歳にして古式な真言宗の伝法を悉く灌頂し、弘法大師以来の才と称されます。翌年より、腐敗した高野山の建て直しに着手します。 この年、鳥羽上皇の院宣により「大伝法院」を建立、その後、大伝法院と金剛峰寺の座主を兼任し、高野山全体を統治することになり、本格的に高野山の改革に乗り出します。 当時、真言宗の腐敗を嘆き、書き記した「密厳院発露懺悔文」は、現在も真言宗各派に於いて、宗教家の自覚と自戒を促す経文として、広く唱えられています。
覚鑁は強行に高野山の改革を押し進めますが、これに反発した僧派閥と激しく対立し、1140年、ついに覚鑁の自所、金剛峰寺境内の密厳院が急襲され焼き討ちに遭い、高野山を追放されてしまいます。なお、この際、覚鑁の命を狙った刺客が、密厳院本尊の不動明王像の背後に覚鑁が潜んでいると判断して斬りつけたところ、像から血が流れたのを見て驚き退散し、覚鑁は一命を取り留めたという、有名な「きりもみ不動」の伝説が生まれました。
高野山を追われた覚鑁は、弟子と共に根来山に退き、根来寺を建立、大伝法院や密厳院を移して、独自の教義を展開します。
1143年、覚鑁は死去しますが、その後、弟子頼瑜を中心に覚鑁の教義を発展させ、「新義真言宗」へと発展します。新義真言宗の本山、根来山は、後に豊臣秀吉との確執の末に討伐を受け壊滅します。根来山を逃れた僧侶達は、京都智積院・大和長谷寺に逃れ、そのままそこを拠点とし、それぞれ真言宗智山派・真言宗豊山派と称して現在に至ります。また、根来山は、1623年、紀伊藩主徳川頼宣の許可がおり、復興に着手し、寛政・文化・文政年間頃に復興を果たし、現在に至ります。
「日本人のお墓」という視点から覚鑁上人を見た場合、大きく二つの功績を挙げることができます。ひとつは「五輪塔」の生みの親であるということ。もうひとつは真言密教と浄土思想を融合させて「真言念仏」をうち立てたことです。というのは、浄土思想とは「死後の思想」に他ならないからです。
井上光貞氏によれば、覚鑁は高野山の本寺出身ではなく、外来の浪人であり、山内の上人と交わりの深い人であったことは注目すべきこと(『日本古代の国家と仏教』)としています。高野山の最高位である金剛峰寺の座主にまでなった覚鑁ですが、元来「真言念仏の別所聖」即ち「高野聖」であったことが、彼の思想と行動に決定的な影響を与えたと思われます。高野聖であったことをバックボーンとして、覚鑁は真言と念仏の同一性を唱え、「五輪塔」に「死後の即身成仏」の意味を込め、また死後と現実世界の浄土に、本尊の大日如来「密厳浄土」をシンボルとする密厳院(念仏所)を高野山に建立したと思われるのです。
この覚鑁の生み出した「五輪塔」と「真言念仏」については、次回以後に詳しく述べることとします。
第十四回 「源信その二」・・(平成19年4月1日)
前回のコラムで、「二十五三昧会」の取り決めごと『横川首楞厳院二十五三昧起請』十二箇条を掲載しました。今回は、起請に見られるお墓と葬送に関する言葉について、書いてみたいと思います。
まず、「光明真言」による土砂加持です。
『不空羂索毘廬遮那仏大灌頂真言一巻』というお経に、次のような言葉があります。 「もし過去にどんな重罪を犯しても、この真言を二、三、七遍聞くだけで、たちまち一切の罪障は除滅される。…もし人が重罪を犯して地獄や餓鬼など諸悪道に堕ちてもこの真言を百八遍唱えて土砂加持をし、使者の遺体の上に撒けば、この真言の神通力で、一切の罪障は除かれ、西方極楽浄土に往き、蓮華の花に化生して菩提を得ることができ、決して諸悪道に堕ちることはなくなる。」 源信の『起請』や先の良源の『御遺告』は、この経典に依っていることがよくわかります。この真言は、真言宗で最も重要視されただけではなく、浄土宗でも重んじられたようです。鎌倉時代の代表的な仏教説話集『沙石集』に、興味深い説話がありますので、大雑把に紹介します。
ある浄土宗の学僧が「亡き人の魂の菩提を弔うには、どの教えが勝れているか」と朝廷より質問を受けます。僧は「宝篋印陀羅尼」と「光明真言」が勝れていると答えます。弟子はこの返答を聞いて不満に感じ、「念仏こそ広大な善根、無常の功徳なはず、師は浄土宗の僧なのに、どうして他宗の教えを誉めるのか。」と疑問をぶつけます。 これに、僧は次のように答えます。「念仏して願いがかなうのは、すべて念仏に善根の功徳があるからで、ほかの教えもかなわない。しかし地獄に落ちるほどの重罪人が往生するには、高僧に会って十念を唱えて、初めて極楽に生まれることができる。そのような機会のない重罪人の子孫が、宝篋印陀羅尼を七遍くり返して廻向するだけで、重罪人は極楽へ生まれ変わり成仏できる。光明真言は、地獄に堕ちて苦しむ死者の魂に、この真言を一遍唱えて廻向すると、阿弥陀仏が極楽世界へと引導する。また、亡き人の墓所で、この真言を四十九遍唱えて廻向すれば、阿弥陀仏はこの霊を背負って極楽世界へと引導する。またこの陀羅尼を見て土砂を加持すること一百八遍、土砂を墓所に散らし、死骸に散らせば、土砂から光が放たれ、霊魂を救って極楽へと送る。これらにはいずれも典拠となる経典や解説書があるのだが、念仏にはこうした明確な典拠がない。だから念仏のことは答えなかったのだ。
各宗派のお墓に「宝篋印塔」が建てられる理由、「光明真言」をはじめとする陀羅尼やお経をお墓に収める意味、墓地の地鎮祭に光明真言で清めた土砂を用いたり、一部の地域で見られる、葬儀の際に使者や棺桶に「御土砂」をかける風習、これらの意味は、この話から理解されるかと思います。 次に、墓所の「安養廟」について見ていきましょう。
安養廟は、今回取り上げた十二箇条の『起請』より前、慶滋保胤が撰した『起請八箇条』では「花台廟」と書かれています。いずれも二十五三昧会の墓所の名前で、「安養」とは「浄土」のこと、「花台」はおそらく「蓮華台」のことと思われます。 『起請』の当該箇所の解説を読むと、高僧に墓所を占ってもらい、陰陽師を招いて地鎮法をおこなわせ、卒塔婆を一基建てて真言でその地を鎮めなくてはならない、と記載されています。当時は映画でもおなじみの陰陽師が活躍した時代で、日時や方位の吉凶に病的なほどこだわった時代ですが、その影響か、本来占いとは無縁なはずの僧侶が、墓地に限っては占いをおこなってます。もっとも、『日本書紀』仁徳天皇の頃から墓地を占う記録は残っていますので、日本の伝統習慣を踏襲しているとも考えることができます。 また、源信『起請』も慶滋『起請』のいずれにも卒塔婆一基を建てることが記載されています。これは源信の師・良源の「御遺告」を踏襲したものと思われますが、お墓の慣習として考えると、この二十五三昧会の『起請』が「骨を修めないお墓」としての「供養塔」の原点となるのではないでしょうか。
「追善供養」についても、良源の「御遺告」が、弟子の墓参を想定していたことを踏襲したと考えられます。井上光貞『日本古代国家と仏教』(岩波書店)では「二十五三昧会は、生者と死者からなる結縁衆の念仏・追善の結社であった」とあり、速水侑『日本仏教史・古代』(吉川弘文館)には「保胤の『八箇条起請』は…『往生要集』に見られない葬送追善の行儀の規定も含んでおり…結社の死者の葬送追善の問題は避けて通れなくなった」とあります。現在私たちがおこなっている追善供養の原点はまさにここにあると言えます。 そして、これは重要なことですが、源信自身は「観想念仏」を重視していましたが、追善の際の念仏はどうしても皆で声を挙げて唱える「称名念仏」にならざるを得ません。臨終・葬儀の際の「称名念仏」といえば空也が思い出されます。空也と源信・保胤との関係については、『今昔物語集』や『発心集』といった史料には、師弟関係にあったことを示す記載が見られます。直接的に関係があったかどうかは定かではありませんが、二十五三昧会の活動に、良源以外の先達の功績が取り入れられていることは明らかに見て取れると思われます。
第十三回 「源信その一」・・(平成19年3月1日)
いい加減しつこいと思われるかも知れませんが、鎌倉仏教全体に見られる特徴として「仏教の複雑膨大な教えの中から、人々が本当に救われるエッセンスを抽出し、教え広めた」ことが挙げられます。そして、多くの宗派が、平安末期に盛んになった浄土教の教えや精神を反映して生まれてきたことも、すでに何度も述べてきました。
源信(942~1017)は、浄土教の生みの親とも言える存在です。その著作『往生要集』は、日本浄土教のバイブル的存在と言えます。まずは序文より、その大まかな内容を見てみましょう。原文は漢文ですが、なるべく平易な文章に改めてみました。
***************************************************************************
往生極楽の教えとその実践は、濁世と末世には目となり足となる。出家者も在家の者も、また身分の貴賤も問わず、誰も皆最後はここに行き着く。だが顕教と密教の教えは必ずしも同じではなく、仏や浄土を具体的に観想するにも、仏の教えを理論的に観想するにも、非常にたくさんの実践法があって、知恵の優れた者や精進できる者は難なくできるだろうが、私のような頑迷で愚かな人間にはとてもそんなことはできない。だから『念仏』だけの分野にしぼって、わずかだが教典や論書から肝心な文章を集めた(これが書名の由来)。これによるならわかりやすく簡単に実践できるだろう。全体を十章、全三巻に分けた。
一、厭離穢土(穢れたこの娑婆世界を厭い離れることについて)
二、欣求浄土(極楽浄土に生まれることを願い求めることについて)
三、極楽証拠(極楽をすすめる典拠について)
四、正修念仏(正しい念仏の実践について)
五、助念方法(念仏を助ける方法について)
六、別時念仏(特定の期日におこなう念仏について)
七、念仏利益(念仏によって受ける利益について)
八、念仏証拠(念仏をすすめる典拠について)
九、往生諸業(極楽往生するための色々な実践法について)
十、問答料簡(問答による疑問点の解明)
これを座右に置いて、忘れないようにしたいものだ。」
***************************************************************************
四万八千巻とも言われる、膨大な仏典の中から、念仏往生に関わるエッセンスだけを取り出し、貴賤を問わず極楽浄土へ至る道を解き明かす。こう書かれた序文に、その後の鎌倉仏教に共通する精神を読みとることができるかと思います。
さて、源信の唱えた「念仏」は、大きく「平生の念仏」と「臨終の念仏」の二つに分け、とりわけ「臨終の念仏」を重んじました。「臨終」とは言うまでもなく死の間際のこと。臨終の時に念仏をすすめること(臨終観念)を重視して、自身の臨終の際の心得にも書き記しています。彼のこうした「臨終行儀」の尊重は、すぐに大きな反響を呼び、賛同する僧侶や在家の貴族ら二十五名により、『往生要集』が完成した翌年(985)には、すでに念仏往生を願う結社「二十五三昧会」へと繋がります。
「二十五三昧会」は源信と、『日本往生極楽記』の著者、慶滋保胤が中心となって結成された念仏結社です。会の講式(取り決めごと)は慶滋保胤らによって何度か出されますが、最終的には源信の『横川首楞厳院二十五三昧起請』十二箇条にまとめられます。この内容は、後に日本全国で臨終から葬儀・お墓のあり方に大きな影響がありました。なので、少々長くなりますが、以下に現代語訳の要旨を掲載したいと思います。
一、毎月十五日の夜に「不断念仏」をおこなう。
一、毎月十五日正午を過ぎたら念仏をし、それまでは『法華経』を講じる。
一、十五日夜に集まった人の中から順番を決めて仏前に灯明をささげる。
一、『光明真言』で加持した土砂を死者の遺骸に置く。
一、二十五三昧のメンバーは、互いに永く父母兄弟の気持ちを持つ。
一、二十五三昧のメンバーは、これを発願した後は、身・口・意の三つの行い(三業)を慎まねばならない。
一、メンバーに病人がでたときは、心を配ってやる。
一、メンバーに病人がでたときは、当番を決めて看護し、見舞いをする。
一、小さな建物を建てて、これを「往生院」と名付け、病人を移すこと。
一、あらかじめ優れた土地を占っておいて「安養廟」と名付け、卒塔婆一基を建てて、我らメンバーの墓所とすること。
一、メンバーに死者がでたときは、葬儀をおこない、念仏を唱えること。
一、この取り決めに随わず、怠ける者があるときは、メンバーから外すこと。
二十五三昧会は、極楽浄土への往生を願う仲間達が、横川首楞厳院で、念仏と『法華経』購読を中心とした信仰生活を送り、結束の固い同志意識のもと、病人の処方・臨終時の対応・墓所や墓の準備・埋葬方法とその根拠・死後の「往生の確認」とその対処について、綿密に連携した組織として活動しました。
さて、これらの史料の中に見える、お墓や葬儀に関する記述については、少々長くなりますので、次回、触れたいと思います。
第十二回 「良源」・・(平成19年2月1日)
良源(912~985)は、第十八代天台座主として、比叡山延暦寺中興の祖として知られる僧です。諡号は「慈恵大師」、正月三日になくなったことから「元三大師」とも呼ばれます。
彼は良くも悪くも処世術に長け、弁論の立つ人物だったようです。最澄直系の弟子ではないにも関わらず、「応和の宗論」など、南都仏教の論客と争論して論破したり、村上天皇の皇后の安産祈願をおこなうなどして頭角を現していきました。良源が天台座主に就いた当時、延暦寺は度重なる火災のために、根本中堂をはじめとする多くの堂塔を消失し、荒廃した状態にありました。これに伴って僧侶の風紀も乱れていたのですが、「二十六ヶ条起請」を公布して僧侶の規律維持に勉め、摂関家からの多くの寄進を得て、延暦寺の復興に尽力しました。比叡山の三塔十六谷は、まさに彼の時代に完成したのです。
良源の活動によって、延暦寺は他の宗派を圧倒し、末寺や荘園も増大して世俗的にも強大な存在となりました。しかしこの結果、延暦寺には多くの貴族の子弟が入山・出家するようになり、彼らが座主や高僧の地位を独占するようになります。また巨大に膨れ上がった僧侶集団は、以後、門閥化が進み、結果、良源が延暦寺の俗化の基を作ったとも言えます。 良源は様々な形で民間信仰の対象となっており、「豆大師」「角大師」とも呼ばれ、魔除けのお守りにもなっています。またおみくじを考案した人ともされており、様々な伝説が残っています。
さて、彼のお墓や葬儀に関する業績として注目すべきは、なんといっても比叡山浄土教の拠点となった「横川常行堂」を発展させたことと、『往生要集』を著した源信の師であったこと、と言えるでしょう。 中国の天台宗では、「四種三昧」と総称される、四種の修行法が説かれておりますが、日本の天台宗では、このうち、「常行三昧」と「半行半座三昧」の二つが重視されました。簡単に言いますと、「常行三昧」とは「念仏行」であり、「半行半座三昧」は「法華行」です。横川常行堂はその名の通り、念仏行をおこなう場所です。ここから良源の多くの弟子が巣立っていくことになります。横川常行堂で注目すべきは、はじめて「称名念仏」がおこなわれたことです。ここにまさに鎌倉仏教の端緒を見ることができます。天台宗の教えそのものが、法華経と浄土教を柱としていることは、すでに度々書いてきたことですが、「南無阿弥陀仏」と唱える称名念仏による常行は、まさに良源の時代に始まったことで、より直接的な影響を見ることができます。 一方、お墓について見ますと、彼の遺言『慈恵大僧正御遺告』に、以下のような言葉があります。わかりやすく現代語に改めてみました。
(私は)生前に石卒塔婆をつくる段取りをしておきたい。もしそれが私の死に間に合わないときは、しばらくは仮の卒塔婆を建て、その下に三四尺ほど掘り下げて墓穴をつくり、穴の底に骨をおいて土で埋めよ。そして四十九日のうちには石卒塔婆をつくって建て替えよ。この石卒塔婆は弟子のおまえたちが時々来て礼拝するための目印であるから、卒塔婆の中には『随求陀羅尼』『大仏頂陀羅尼』『尊勝陀羅尼』『光明真言』『五字真言』『阿弥陀陀羅尼』などの真言を安置せよ。生きているうちにそれを書きたい。
ここにでてくる石卒塔婆が、建立当時どのような形であったかは不明ですが、形はさておいて、この遺言の中でとても重要なのは、自らの死後、弟子が墓参することを念頭に置いている、ということ。また墓参によって、自分と弟子のために、滅罪の効力のある真言を卒塔婆に納めたことの二点です。
おそらくこの頃から、仏教的な建墓・墓参・供養が、生者と死者が共に滅罪され、ひいては極楽往生の思想へと繋がる兆候が見えはじめていると言えるのではないでしょうか。
第十一回 「空也」・・(平成19年1月1日)
空也上人の像と言えば、右手に鉦鼓・左手に鹿角杖、粗末な身なりの立像で、その口からは「南無阿弥陀仏」を表す六位の仏を吐き出す姿ですね。
生没は諸説あって判然としませんが、おおよそ10世紀中頃、平安中期に在俗の修行者として諸国を巡り、布教と社会事業に専心して、貴賤を問わず幅広い帰依者を得ています。
空也上人の仏教史上に於ける最大の功績は、民間に浄土教、もっと具体的には念仏を広めたことにあります。彼の立像の口から仏様が吐き出されているのは、まさにことことを象徴しております。このため、彼は「阿弥陀聖」「市聖」と称されて民間信仰の対象となり、記録では京都の六波羅蜜寺で生涯を終え、その墓も六波羅蜜寺にあるのですが、各地に彼の墓が建立されて、今もなお信仰の対象となっております。
また、彼は踊念仏・六斎念仏の祖ともされておりますが、これは、空也が経文中に見い出した釈迦の説教に感激し、踊り出したという経験から、そのことをヒントに生まれたといわれています。
空也自身は、例えば行基のおこなった東大寺建立の資金集めのような勧進をおこなった形跡がありません。より「念仏遊行」の色彩の濃い活動は、彼自身への信仰はもちろん、後世の鎌倉仏教の普及の大きな礎となっていることは否定できません。
さて、もうひとつ、空也の業績として大きなものがあります。平安中期第一級の文人貴族であった源為憲は、空也への弔辞として『空也誄』という文章を残しています。この序文に次のような文があります。
「曠野古原に、若し委骸有らば、之を一処に堆みて、油を灌いで焼き、阿弥陀仏の名を留む」
今でこそ、遺骸に向かって念仏を唱えたり、火葬の際に念仏を唱えることは、ごくごく当たり前に見られる光景ですが、所謂この「称名念仏」は、空也によってはじめておこなわれ、空也によって世に広められたのです。
前号でお話しした行基と共に、空也上人は、日本の仏教が死者を供養し、死後の幸福を願って積極的に死者に関わる伝統の一端を為し、身分の貴賤を問わず広く浸透させていったという意味で、非常に偉大な存在と言えます。
第十回 「行基」・・(平成18年12月1日)
日本中世には、高野聖に代表される、各地を歴訪して勧進と呼ばれる募金活動の一環として仏教の普及活動をおこなった僧侶集団がいくつか存在しました。
今回取り上げる行基菩薩は、その先駆的な存在と言えるでしょう。
行基は天智天皇の時代(668年)に生まれました。10代半ばで出家し、法相宗等の教学を学び、やがて集団を形成して関西地方を中心に貧民救済や治水、架橋などの社会事業活動をおこないました。彼は民衆を扇動する者として弾圧を受けましたが、これは、彼を信奉する民衆が多かったことを物語っています。
723年に、自発的な開墾を奨励する「三世一身法」が発布されると、池溝開発を始めとする行基の活動は急速に発展し、その存在を無視できなくなった朝廷は、731年、ついに得度を許し、738年には彼の布教活動が公認されます。741年までに、行基とその仲間たちが畿内一帯に造った施設は、寺34・尼寺15・橋7・池15・溝7・堀4・樋3・湊2・直道1・布施屋9か所に及んだということです。
時の天皇、聖武天皇は行基に深く傾倒し、741年には大仏建立の勧進(募金活動)に起用し、745年には彼のために新設した「大僧正」の位を授け、更には「大菩薩」の称号を授けています(749年)。それから間もなく、行基は大仏完成を見ることなくこの世を去ります。その亡骸は、遺言により火葬に付されたとのこと。
さて、行基に限らず、後世の様々な「聖」集団も含めてですが、民衆生活の中に仏教が広まっていく課程で、彼らの貢献は非常に大きなものがあったと言えます。聖の集団は本寺からの衣食住の支給がないために、生活のほぼすべてを勧進に依存していました。勧進をうける替わりに、彼らは社会事業活動をおこなっておりましたが、その中には葬送をおこなう集団もおり、他には高野山納骨をおこなう集団もありました。こうした聖集団の仏教的な活動によって、民衆が仏教に触れる機会は非常に増えたと思われます。
もちろん、学校教科書に記載されているように、鎌倉仏教の隆盛が現在に至るまでの、日本の仏教信仰へ多大な影響を与えたことは否定しませんが、その前段階としての、聖集団の活動は無視できないと思います。
こうした聖集団の先駆的な存在であった行基の集団にも、当然ながら、葬送に関する活動がおこなわれていたと考えることができるかと思います。
五来重という宗教民俗学者が、行基の葬送に関する活動について、興味深い仮説を立てております。以下に、私見を交えてその概要をまとめてみました。
行基の生きた時代は、ちょうど古墳文化が廃れてきた時代に重なります。大化改新後に発布された「薄葬令」によって墳墓の規模が縮小し、やがて古墳そのものが造営されなくなります。ほんの数世代までは巨大な古墳が造営され、関連する祭祀にも非常に多くの人間が関わっていたわけですが、こうした時代変化に伴って、古墳に関わってきた多くの氏族が、その職を失ったはずです。五来氏は、こうした氏族集団が、行基の集団に加わったのではないか?という仮説を立てました。実際、723年に、行基の集団が急に大きくなったと思われる史料が残っています。また、行基の足跡には、数多くの土木事業が残されております。こうした活動には、古墳造営で培った技術を持った集団が大いに貢献した、とは考えることはできないでしょうか。そして彼ら技術者集団は、元来が葬墓に関わってきた人々です。行基の仏教的な活動の中にも、彼らの影響は残されていたはずです。
また行基は、自身を火葬に付すことを遺言したように、火葬を推進したと思われます。行基は、近畿を中心に「四十九院」と呼ばれる、小規模な道場のようなお寺を建てたとされています。この四十九院すべてには火葬場があったという説もあります。
そして、この四十九院というのは、本来は弥勒菩薩が居住する「兜率天」の四十九の内院をさします。行基の四十九院も、これにちなんだものと考えられます。というのは、奈良時代以降、弥勒信仰が盛んになってくるからです。
日本の仏教墓には、四十九院と呼ばれる、外柵として木や石の杭を打ち込み、これに横棒を通した独特のスタイルがあります。高野山奥の院墓地では特によく見られるスタイルですが、これも弥勒信仰にまつわるものではないかと思われます。
ところで、この、墓の回りに杭を打ち込んで外柵とするお墓のスタイルは、日本古来の「モガリ」の習慣であると言われます。四十九院という日本独自のお墓のスタイルに、日本の伝統習俗と、仏教思想の融合を見て取ることはできないでしょうか。そして、こうした文化的融合に、行基集団の活動の影響を見ることは、行きすぎた想像でしょうか。
第九回 「聖徳太子」・・(平成18年11月1日)
今月からは、日本の仏教墓の歴史に大きな影響を与えたと思われる人物について、書いてみたいと思います。
最初は聖徳太子。
聖徳太子といえば、日本史上もっとも偉大な人物の一人として、信仰の対象にもなっている人物です。
イエス・キリストや釈迦にも似た出生譚に始まり、太子の血縁である蘇我氏と共に、仏教保護に努め、律令国家の礎を築いた人物とされています。四天王寺や法隆寺建立、冠位十二階・十七条憲法の制定、『三経義疏』等の著作を残し、『天皇紀』『国記』などの編纂事業といった歴史的な業績の他、全国各地に、聖徳太子建立とされる寺院があり、「豊聡耳皇子」と称される逸話等、多くの伝説が残されています。ただ、聖徳太子に関する史料は、720年に成立した『日本書紀』よる古いものは存在しません。『日本書紀』成立の時点で、既に聖徳太子没後100年近くが経っていることや、『日本書紀』以前に、既に聖徳太子ゆかりの建造物の多くが消失していることもあって、実際のところ、どこからどこまでが史実として認められるのか、定かではありません。それどころか、実在を疑う説も存在します。また学校教科書では、これまでずっと「聖徳太子」と表記されてきましたが、新課程では「厩戸王(聖徳太子)」となり、次期教科書からはついに「聖徳太子」の呼び名が消えることになります。
さて、これほどの伝説的な人物の逸話のひとつをこれから紹介するわけですが、記載のある史料は平安時代成立と思われる書物。当然ながら多分の脚色はあると思われますし、全くの作り話かも知れません。なので、聖徳太子に仮託された、当時の風習を知る史料として読むことも可能です。
聖徳太子は47歳の時に、生前に建立させていた自分のお墓に入って、お墓の形を見て、子孫断絶の形と判断し、細かに指図したという話(『聖徳太子伝略』)があります。このお話で注目すべき点は二つあります。ひとつは「墓相」という考え方が、少なくとも平安時代当時には存在したということ。そしてもうひとつは、生前に自分のお墓に入るという行為。これは現在でも、火葬場の開場式の際に、多くの人達が火葬窯に入る風習を連想します。仏教ではこのような行為を「逆修」といいます。いわゆる「生前葬」も逆修のひとつといえるのでしょうが、「生きているうちに自分の墓に入る」、つまり、一旦死んだことにして再生することで、それまでの罪が滅び、不幸の源はたたれるので、健康と幸福が得られるという考え方、もっと言えば民間信仰とも言える行為に繋がります。仏教の各宗派にも同様の行為があります。曰く「五重相伝」(浄土宗)・「伝法」(融通念仏宗)・「帰敬式」(浄土真宗)・「結縁灌頂」(真言宗)など、生前に法名や戒名を受ける行為。信州善光寺の「戒壇めぐり」などもこれに含まれます。温泉街や火山の観光地に間々見られる「○○地獄」や「地獄巡り」といった言葉にも、この考え方が含まれているのかも知れません。
聖徳太子の伝記として残された史料ですが、既に述べたように信憑性が疑われる説話でもあります。ただ、その真偽はともかくとしても、こうした擬死体験や行為に関する風習が聖徳太子に仮託されて語られる意味はなにかしらあるわけです。
日本に於ける仏教の、最初の偉大なる庇護者としての聖徳太子。擬死体験としての「逆修」という仏教儀式の普及活動のシンボルとして利用されたのかも知れませんね。
- サイト内検索
- Feeds
- Meta

